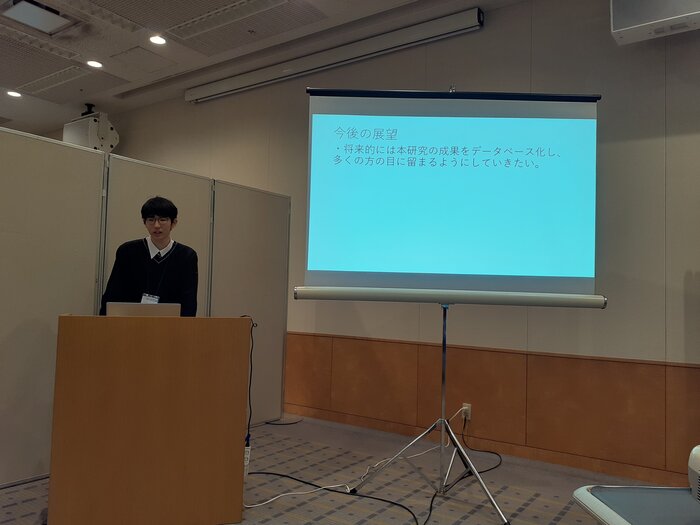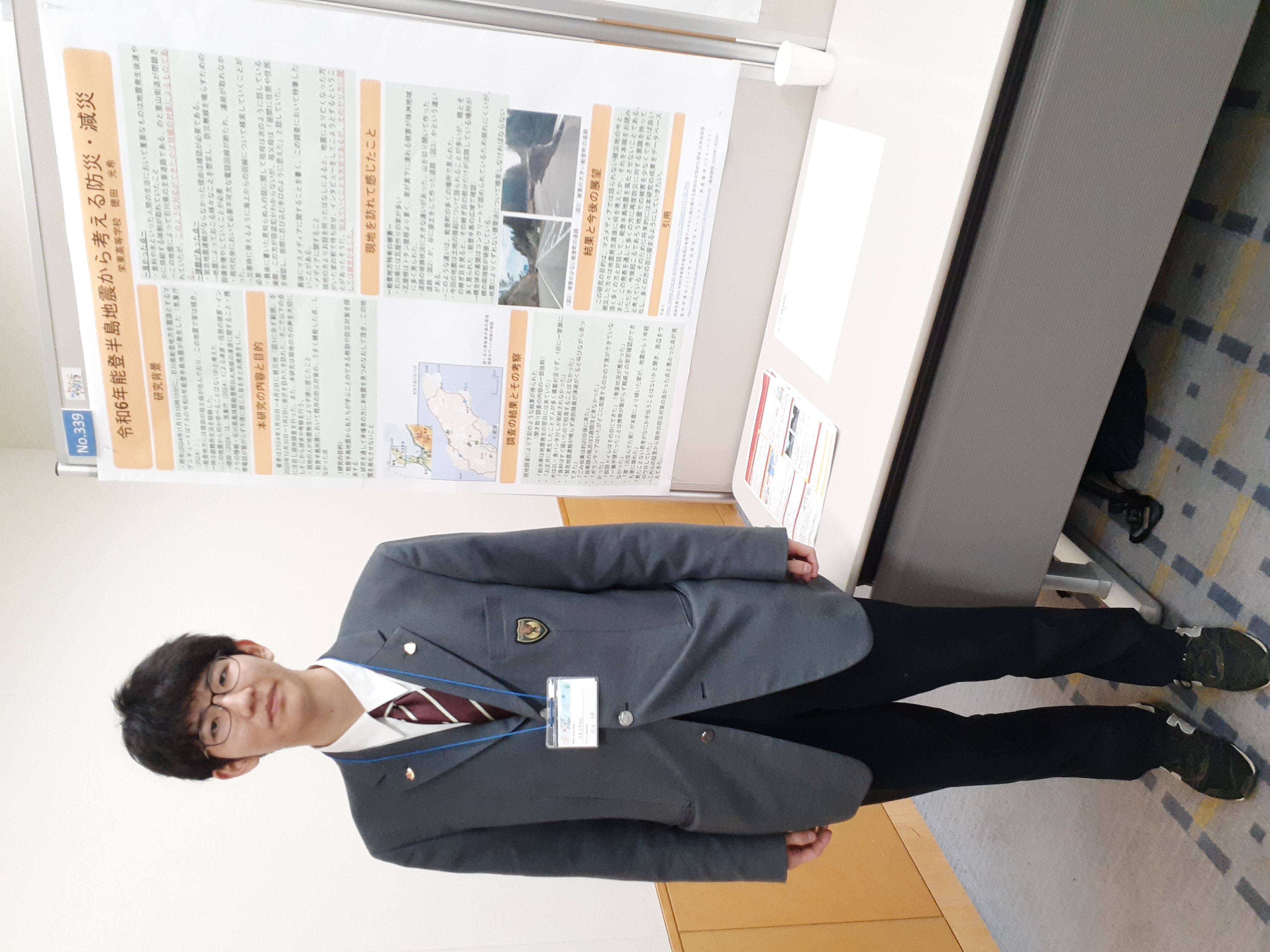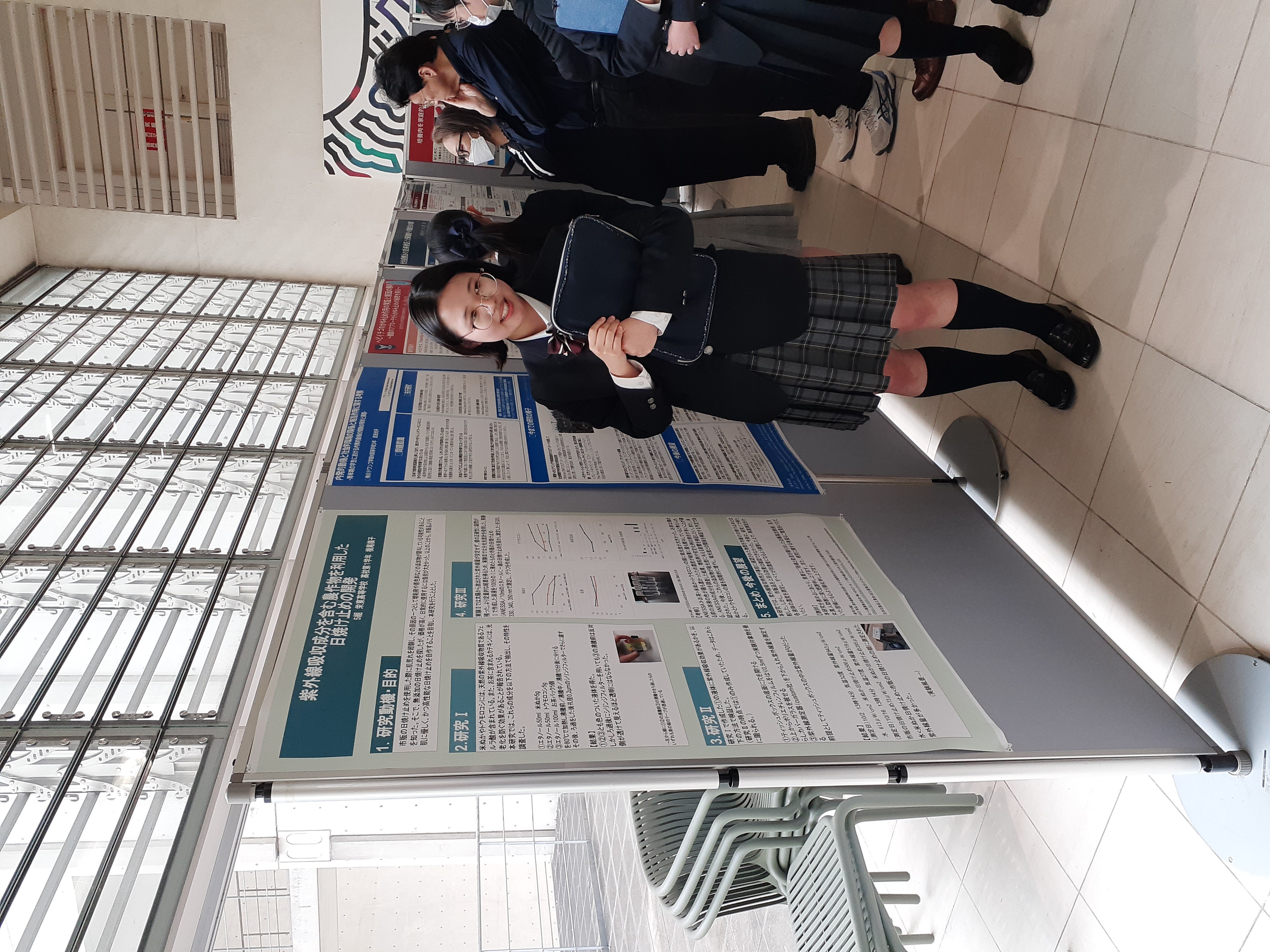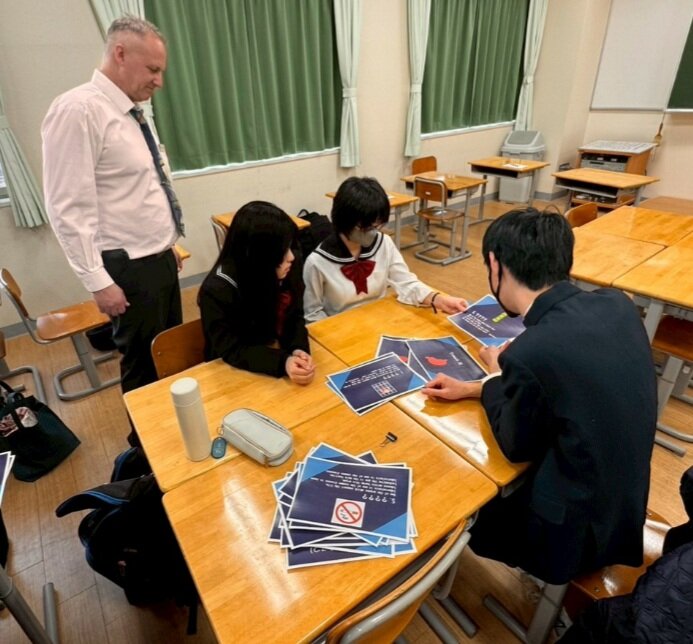3月28日につくば市にあるKEK(高エネルギー加速器研究機構)にて行われた職場見学に行ってきました。参加メンバーは中1から高2の理科研究部のメンバー6名です。一日にわたって様々な施設を見学させていただきました。最先端の研究や携わる研究者たちを前に、生徒たちは目を輝かせて溢れる様々な質問を投げかけていました。また、東京ドーム33個分もある敷地の半分くらいの大きさ実験装置(BelleⅡ)の内部に入るという貴重な体験もさせていただきました。

写真)KEKでの研究概要とミューオン粒子についてご講義いただきました。

写真)BelleⅡの内部を案内してもらいました。部員の目の輝きが止まらなかったですね。

写真)実際に使っていた加速器の一部を使ってBelleⅡの特徴や、研究展望についてお話いただきました。
以下、生徒による感想文です。
中学2年(当時) 仲田 くん
今回、「KEK」が主催している職場体験で、素粒子の理論や現在行われている研究について研究者の方々から直接お話をいただくことで、様々な知見を得ることができました。
午前中に行われた講義では、特に「ミューオン」という素粒子の特性やその特性を活かした物質解析について詳しい話をいただきました。宇宙の様々な事象を記述するために素粒子を見る、というだけではなく、素粒子を使ってマクロな物質を見る、という素粒子研究に関する新たな一面を知ることができ、新たな学びにつながりました。また、「ミューオン」がどのように物質と相互作用を起こして、どのようにしてそれを観測しているかという話も大変興味深かったです。
午後に見学させていただいた「BelleII測定器」とその周辺にある設備には、あまりの大きさに圧巻されてしまいました。残念ながら、工事中で細部まで見ることはできなかったのですが「KEK」の一般公開のときには入ることができなかった場所にも入らせてもらい、研究者の方に「BelleII測定器」の内部構造や「BelleII実験」で行われていることを説明していただきました。「BelleII測定器」で粒子の飛跡を、ある実験結果を基にアルゴリズムを使って測定しているということには特に驚きました。
今回の職場体験を通して、素粒子に関する実験とその活用について学びを得ることで、自分の興味の幅が広がりました。また機会があれば「KEK」に伺いたいです。
高校1年(当時) 宮下くん
3月29日に、高エネルギー加速器研究機構を訪れ、実際にそこで働いている研究者の方と会い、今行っているBelle Ⅱ実験や素粒子物理学について、その基礎から現在研究が行われている分野まで、様々な説明を頂きました。
講義では、主にミュー粒子についてその性質を、またKEKの誇る世界最大級の加速器について、どのように応用されているか知ることが出来ました。特に、ミュー粒子について、「大きさはないとみなして良いが、質量はある」という性質が印象に残っています。ミュー粒子のその不思議な特性を活かして元素特定に使われていること、ミュー粒子は加速器を用いた衝突実験の副産物であることなど、様々なことを教えて頂きました。
また、その後に行ったBelle Ⅱ実験の見学では、まずKEKで使われている加速器の大きさに圧倒されました。予算400億円ほどで作られている現在の加速器に対し、将来的には予算1兆円規模の次世代型加速器の建設が予定されているそうです。
他にも、Belle Ⅱ実験で使われている素粒子感知器の仕組みや、その精密さも教えて頂きました。ナノメートル単位の誤差で、非常に精密に張り巡らされた特殊な糸で作られた感知器は、構想5年、製作5年のBelle Ⅱ実験のなかで、2年をかけて作られたそうです。
今回、KEKへの訪問で、実際現場で働いている研究者の方と話せたことで、より将来に向けたイメージが出来るようになりました。KEKは昔図鑑で知っていた憧れの場所だったので、今回の訪問でより将来研究者になりたいと思うようになり、大きな刺激を受けました。